これはチだわ。地動説の漫画とか小難しそうだけどキャラが全員魅力的でぶっ飛ぶほど面白かった。
ヒカルの碁は囲碁が分らなくても面白いから凄い
読破した今でも全くルールを理解していない
働く細胞。まさか細胞擬人化漫画出るとは思わなかったしめちゃくちゃ勉強になるのもすごい。
酪農家·農業高校·錬金術という地味テーマをヒット作にした荒川先生と、古代ローマの大衆浴場をあそこまで膨らませたヤマザキ先生は本当にユーモア&教養の塊なんだろなとたまげる
暗殺教室
なんで中学3年生の学園モノに暗殺とかいう物騒な要素が結びついて傑作のまま走り切ったんだ
「あかね噺」かな。
落語は演者の動き目で見て耳で話を聞いて楽しむものなのに絵と文字だけであそこまで表現できてるのもすごいと思ったね。
からかい上手の高木さん 男女が友達以上恋人未満の関係をずーっと描いてるだけの漫画なのに常に面白いの凄い
魔王城でおやすみ
始まった当初、面白いけど睡眠ネタでいつまで続くかな?と感じ5〜6巻で終わるかと思ってコミックを買い始めたら、どんどん話は広がり、アニメ化もして、次巻はとうとう30巻の大台に乗ります
高校の書道部を題材にした「とめはねっ」
そもそも作中に出てくる書が本当に上手な書じゃなければならないという時点で漫画の題材にするには無理があるのに、よく漫画にしたと思う。
灼熱カバディは熱くて、スポーツ物と格闘物合わせたみたいでくっそ面白かった。
だがしかし
駄菓子を題材にするのは驚いた。しかも内容個人的にはめっちゃ好きで面白い
逃げ上手の若君。正直一般認識では知名度が低いと言わざるを得ない北条時行を主人公に据え足利尊氏と言う日本史でもメジャーな人物を敵側で描こうと決めた松井先生の着眼点は凄いと思う
やっぱ王道って自分でつくるもんなんだって…
マイナー素材で作品作って、ヒットしたら素材の魅力が万人に知れ渡る。最高じゃないの
アイシールドの原作・作画コンビが強すぎる
アクタージュ、残念でしたね
コミックス買って読みたいと思ったタイミングがもっと早ければ…
て思う人はたくさんいただろうな
スラダンも当時はバスケ漫画なんて売れないだろうとか思われてたんだけど、ヒットしたことでバスケブーム来たとか
「ちはやふる」とか「この音とまれ」とか「あさひなぐ」とか、日本の伝統的な娯楽や武道を高校部活に持ってくの新しいと当時思った
ハイパーインフレーションは経済という到底漫画向けとは思えない題材を見事に活かしてて面白かった
アニメ化待ってます……
ちはやふる
競技かるたは現実だとスピードとか凄くて迫力あるけどルールがシンプル過ぎるし漫画でどうやったら面白くできるんだと思った
これは『逃げ若』でしょう。『ネウロ』や『暗殺教室』よりもマニアックな題材ですが、アニメ化まで行ったのは凄いですね。
鬼灯の冷徹かな
地獄が舞台なのにコメディ120%でぶっ飛んでて大好き
それで且つ神話とかめちゃくちゃ勉強になる
ボーボボの題材は鼻毛でいいのか…?
あかね噺は落語が題材なのに寄席の空気感とかめっちゃ上手く表現できててすごい
メダリスト
直接対決じゃないし実戦の時間も短いから、他のスポーツ漫画の3倍くらい描くの難しそう
あかね噺とかな。
落語を題材にするのは個人的に衝撃的だった。しっかり面白いし。
そして勝手に上がってく笑点メンバーの格
輸入雑貨商の男がふらっと立ち寄ったお店で料理を食べるだけの漫画。
「美味しんぼ」も連載開始当時の1983年には斬新だったんじゃないかな。料理漫画なのに、主人公が料理人じゃなくて、新聞会社の社員なんだから。

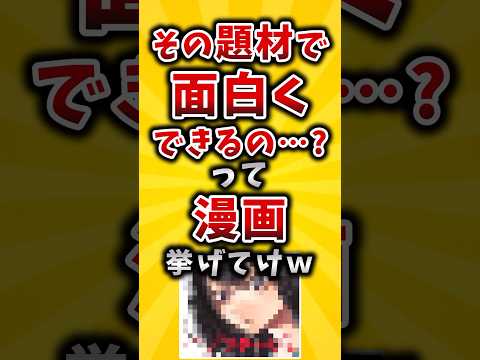
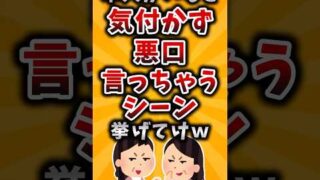



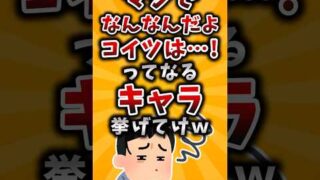
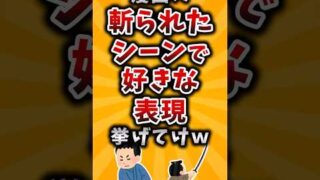

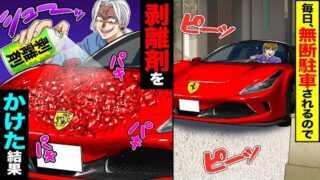

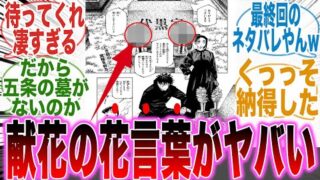
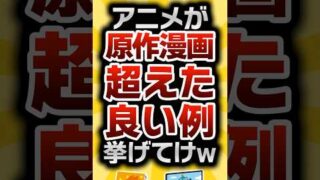
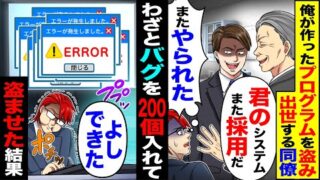
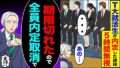



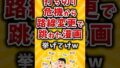

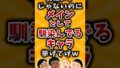
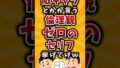

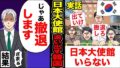
コメント一覧